はじめに
「夜中に吠える」「急に鳴き出す」――
シニア犬と暮らしていると、夜泣き(夜鳴き) に悩む飼い主さんは多いのではないでしょうか。
私も4頭のシニア犬と暮らす中で、夜に不安そうに歩き回ったり、声を上げる様子を目にすることがあります。
最初は「どうしていいかわからない」「何をして欲しいの?」と戸惑いましたが、夜泣き(夜鳴き)の主な原因を勉強して我が家で出来る工夫を重ねることで、わんこも私も少しずつですが落ち着いて過ごせる日が増えてきました。
この記事では、老犬の夜泣き(夜鳴き)の主な原因と、家庭でできる工夫、病院に相談すべきタイミング をご紹介します。
同じように悩んでいる飼い主さんにとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。
老犬が夜泣き(夜鳴き)をする主な原因
認知症による不安や混乱
犬の高齢化に伴って増えているのが「犬の認知症」です。
昼夜の区別がつかなくなり、夜中に歩き回ったり吠えたりすることがあります。
これは後でお話しする生活リズムの乱れも大いに関係する場合が多いので併せて理解することが重要です。
視力や聴力の衰え
暗い中で周囲がよく見えない・聞こえないことが不安につながり、夜泣き(夜鳴き)に結びつく場合があります。
トイレの不安や体の痛み
夜間にトイレへ行きたいのに思うように動けない、または関節や内臓の痛みが夜泣き(夜鳴き)の原因になる場合があります。
生活リズムの乱れ
昼間によく眠ってしまい、夜に目が覚めて活動的になると、飼い主さんを呼ぶように鳴くことがあります。
我が家で気づいたこと
13歳を超えた子は、以前はぐっすり眠っていたのに夜中にソワソワすることが増えてきました。
そこで生活リズムを整えるために日中の日光浴(散歩や日向ぼっこ)を増やし、また「決まった寝床(ベッドやマット)」を用意し、私のそばで寝てもらうようにしたところ、少し落ち着いて眠ってくれるようになりました。
生活リズムを整える事と安心できる居場所を作ることは、夜泣き(夜鳴き)対策の第一歩 だと感じています。
老犬の夜泣き(夜鳴き)対策の工夫
1. 生活リズムを整える
- 昼間に軽い散歩や遊びで体を動かす
- 足腰の弱ってきた子の場合、ペットカートやペットポーターなどの専用器具を利用して日光浴させてあげる
- 寝たきりの子には寝ているベッドを日の当たる場所に移すし日光浴させる
- 夕方にしっかり食事をとる
- 夜は照明を落として「眠る時間」を意識させる
生活リズムを整えるのに日光浴は非常に効果的と言われています。昼間は目覚めて夜熟睡するを心掛けるようにすると生活リズムが整い、夜泣き(夜鳴き)が減る場合もあります。
2. 安心できる寝床を整える
- 足腰にやさしいマットや低めのベッド
- 落ち着けるクレートやサークル
- 冷暖房を使って快適な温度をキープ
今いる場所の不快を訴える場合(ベッドが固くて痛い・暑い・寒いなど)もあります。飼い主さんが良く観察し、思い当たることがあればその不快原因を改善してあげることで夜泣き(夜鳴き)が減る場合もあるかもしれません。
3. 飼い主さんの声掛けやスキンシップ
夜泣き(夜鳴き)が始まったら、優しく声をかけたり撫でたりして安心感を与えます。
ただし、毎回長時間対応すると「鳴けば来てくれる」と学習してしまうので、安心させつつ静かに眠れる流れを意識しましょう。
4. 補助グッズやサプリを活用
- フェロモンスプレーやアロマ
- リラックス用サプリメント
- 防音カーテンや寝室のレイアウト工夫
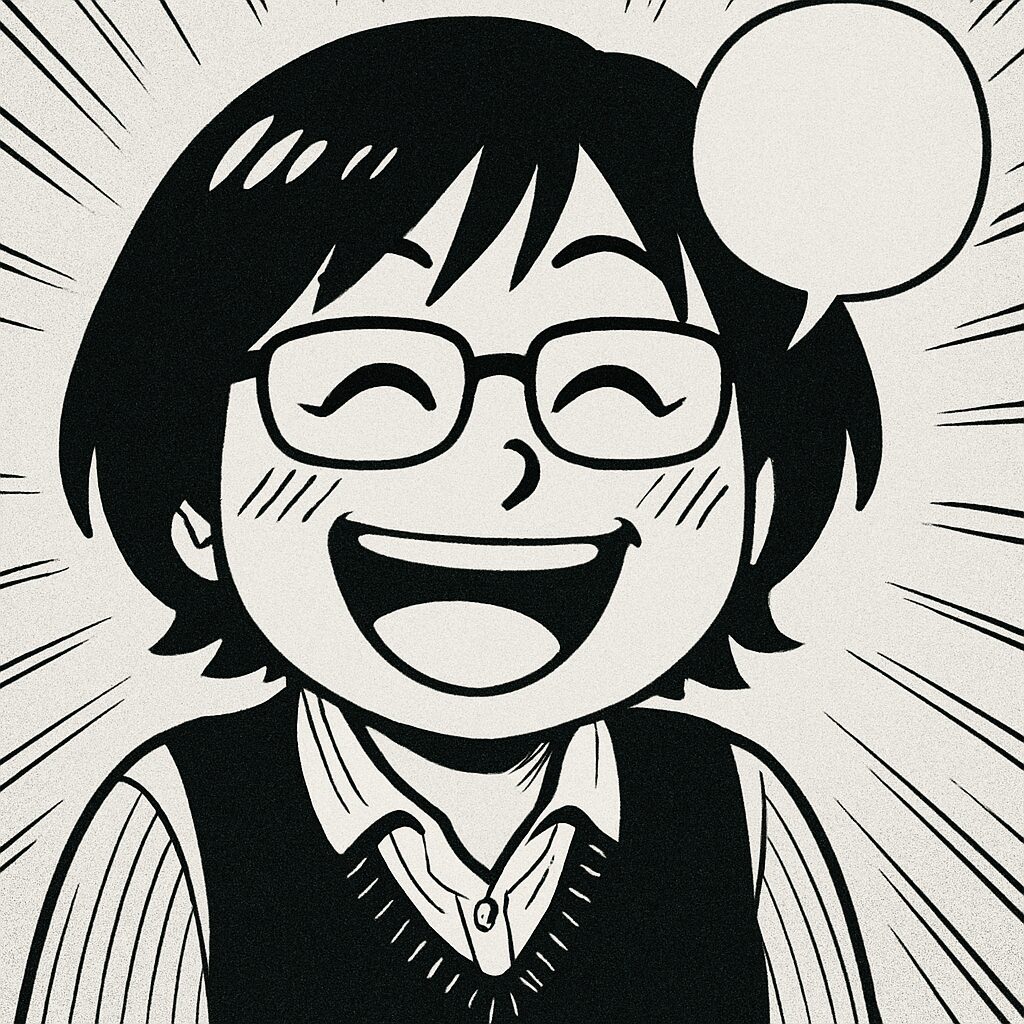
我が家では夜にアロマの芳香浴を行います。リラックス効果のある(ひのき・サンダルウッド・ローズ・ネロリなど)アロマがおすすめです。
病院に相談した方が良いケース
- 毎晩夜泣き(夜鳴き)が続き、家族も消耗している
- 食欲不振や排泄の変化など、他の症状も見られる
- 急に泣き声が増えたり、痛がる様子がある
夜泣き(夜鳴き)が「行動の問題」ではなく「病気のサイン」である可能性もあるため、心配な時は早めに獣医師に相談することが大切です。
まとめ
老犬の夜泣き(夜鳴き)は、飼い主さんにとっても本当に大きな負担になります。
けれども、原因を探り、環境を整え、小さな工夫を積み重ねることで、わんこも飼い主さんも穏やかな夜を取り戻すことができる場合があります。
- 夜泣き(夜鳴き)は「困った行動」ではなく「心や体からのSOS」
- 安心できる環境と生活リズムで改善できることもある
- 無理をせず、必要に応じて病院や介護サービスに相談
愛犬の夜泣き(夜鳴き)は「もうお別れが近い」というサインではなく、これからも一緒に過ごすためのケアの合図です。
どうか前向きに工夫を重ね、穏やかな夜を過ごせますように。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc36f1d.067103ae.4cc36f1e.35c8e0b6/?me_id=1306887&item_id=10002516&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiken-concierge%2Fcabinet%2Franking%2F84100004_10enrank1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc359b7.89eed46e.4cc359b9.334b64fa/?me_id=1222834&item_id=10001956&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchronos-r%2Fcabinet%2Fdescription%2Fselectessentialoil%2Fmainimage6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント