はじめに
シニア犬と暮らしていると「最近少し様子が変わってきたかも?」と感じる瞬間があります。
その中でも、多くの飼い主さんが不安に思うのが 「犬の認知症(犬の認知機能不全症候群)」 です。
認知症は決して珍しいものではなく、長生きする子が増えた今では多くの家庭で向き合うテーマとなっています。
今回は、認知症のサインと工夫、そして飼い主としての心構えについてお話しします。
シニア犬の認知症とは?
犬の認知症は、人間の認知症に似た症状を示すことがあり、脳の老化によって記憶力や行動パターンに変化が見られる病気です。
「夜鳴き」「徘徊」「混乱した行動」などが特徴で、生活に影響を与えることがあります。
よく見られる症状
1. 夜鳴きや昼夜逆転
夜になると落ち着かず吠える、寝ない、逆に昼間にぐっすり眠るといった生活リズムの乱れが出てきます。
2. 徘徊や同じ場所をぐるぐる回る
狭いところを行ったり来たりしたり、同じ方向にぐるぐる回る行動が見られることがあります。
3. トイレの失敗が増える
場所を忘れてしまったり、我慢できずに失敗することが増えるのも認知症のサインです。
4. 反応が鈍くなる
呼んでも気づかない、名前を呼ばれても反応しないことが増えることもあります。
5. 不安感や落ち着きのなさ
家族がそばにいないと不安になったり、落ち着かず鳴き続ける子もいます。
認知症の子にできる工夫
1. 生活リズムを整える
・朝はしっかり散歩や日光浴をさせる
・昼間は適度に活動を入れて夜は眠れるようにする
これだけでも夜鳴きの軽減につながることがあります。
2. 環境を安心できるものに
・家具の配置を変えない
・決まったベッドやマットを用意する
・暗い夜は常夜灯をつける
安心感を与えることで混乱を減らせます。
3. 脳を刺激する遊びを取り入れる
「におい探し」や「知育トイ」など、頭を使う遊びは認知症の進行を遅らせる効果が期待できます。
4. サプリや療法食の活用
獣医師に相談すると、脳の健康をサポートするサプリメントや療法食を勧められることもあります。
必ず専門家のアドバイスを受けながら取り入れましょう。
飼い主さんの心構え
認知症の介護は、身体的にも精神的にも負担が大きいものです。
- 「うるさいから困った」ではなく「不安だから鳴いている」と受け止める
- 完璧に世話しようとせず、便利グッズやサービスを上手に活用する
- 飼い主さん自身も休む時間を持つ
大切なのは「無理をしないこと」。
介護は長期戦になることも多いため、飼い主さん自身の心身の健康を守ることも大切です。
我が家の工夫
我が家の子たちはまだ認知症の症状は出ていませんが、年齢的にはいつ始まってもおかしくありません。
そのため、
- 決まったベッドやマットを用意して安心できる居場所をつくる
- におい探しゲームで脳を刺激する
- 昼間は日当たりの良い場所で過ごさせる
- 朝の散歩で外部の刺激を取り入れる
といった工夫を日常から取り入れています。
「備えあれば憂いなし」──そう思いながら、今のうちから準備をしています。
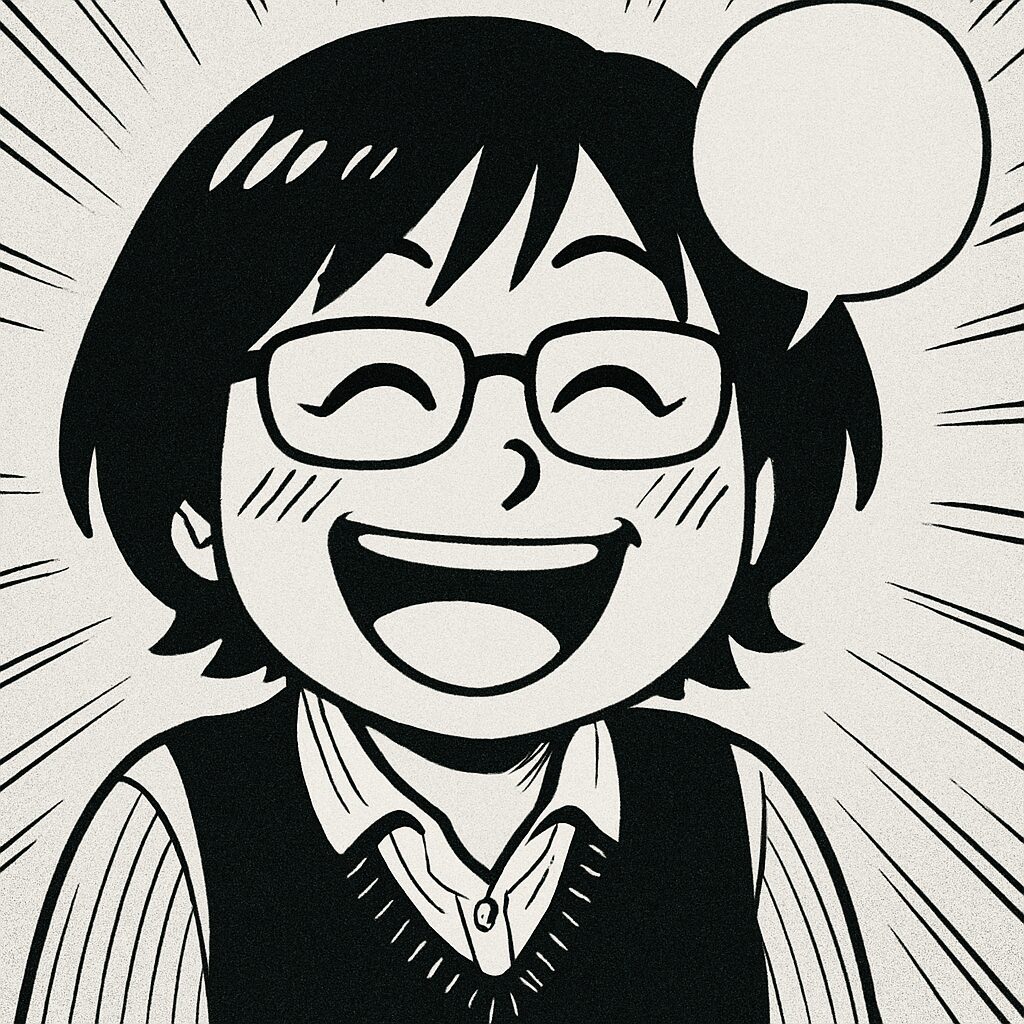
この本には介護ノウハウがびっしり!おすすめの書籍です。
まとめ
シニア犬の認知症は特別なことではなく、長生きの証とも言えます。
- 夜鳴きや徘徊などの症状に気づく
- 環境や生活リズムを整える
- 脳を刺激する遊びを取り入れる
- 飼い主さん自身も無理をしない
こうした工夫を続けることで、認知症ともうまく付き合いながら、愛犬との暮らしを穏やかに保つことができます。
👉 関連記事:『シニア犬の心を元気に保つ工夫』

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c90c466.a737e5d6.4c90c467.986ebb9c/?me_id=1213310&item_id=11886175&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4710%2F47108155.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


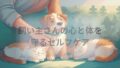
コメント