年齢を重ねたわんこが、夜中に鳴いたり、同じ場所を行き来したり——。
そんな行動を見て「どうしたんだろう」と不安になることはありませんか?
それは、単なる“わがまま”や“癖”ではなく、
**認知機能の変化(いわゆる犬の認知症)**が始まっているサインかもしれません。
認知機能の低下はゆっくりと進むもの。
でも、早く気づき、穏やかに支えていくことで、
わんこの生活の質(QOL)はぐっと保つことができます。
認知機能の変化とは?
犬の認知機能不全(Cognitive Dysfunction Syndrome:CDS)は、
人の認知症に似た状態を指します。
脳の老化によって記憶や判断力が低下し、
時間・場所・人の認識が少しずつ曖昧になっていく状態です。
発症の時期はおおむね10歳前後からが多く、
シニア期後半になるとその兆候が現れやすくなります。
けれど、それは“病気”というよりも、
**「歳を重ねた結果の自然な変化」**と考えてあげることが大切です。
よく見られる認知機能のサイン
次のような行動が見られる場合、認知機能の変化が始まっているかもしれません。
🔹 夜間の行動変化
- 夜中に鳴く、歩き回る
- 昼夜が逆転して夜に活動的になる
🔹 空間認識の変化
- 同じ場所を行ったり来たりする
- 壁や家具にぶつかる、方向転換がぎこちない
🔹 記憶・反応の変化
- 名前を呼んでも反応が鈍い
- トイレの場所を間違える
- 家族を見ても一瞬“誰だろう?”という顔をする
🔹 感情や性格の変化
- 甘えん坊になったり、逆に怒りっぽくなる
- 落ち着かずウロウロする
- 吠え続ける、寂しがる
穏やかに支えるための工夫
認知機能の変化は止めることはできませんが、
進行をゆるやかにし、安心して暮らせる環境を整えることができます。
① 生活リズムを整える
朝・昼・夜の行動リズムをできるだけ一定に。
毎日同じ時間にごはん・散歩・排泄を行うことで、
わんこの体内時計を安定させられます。
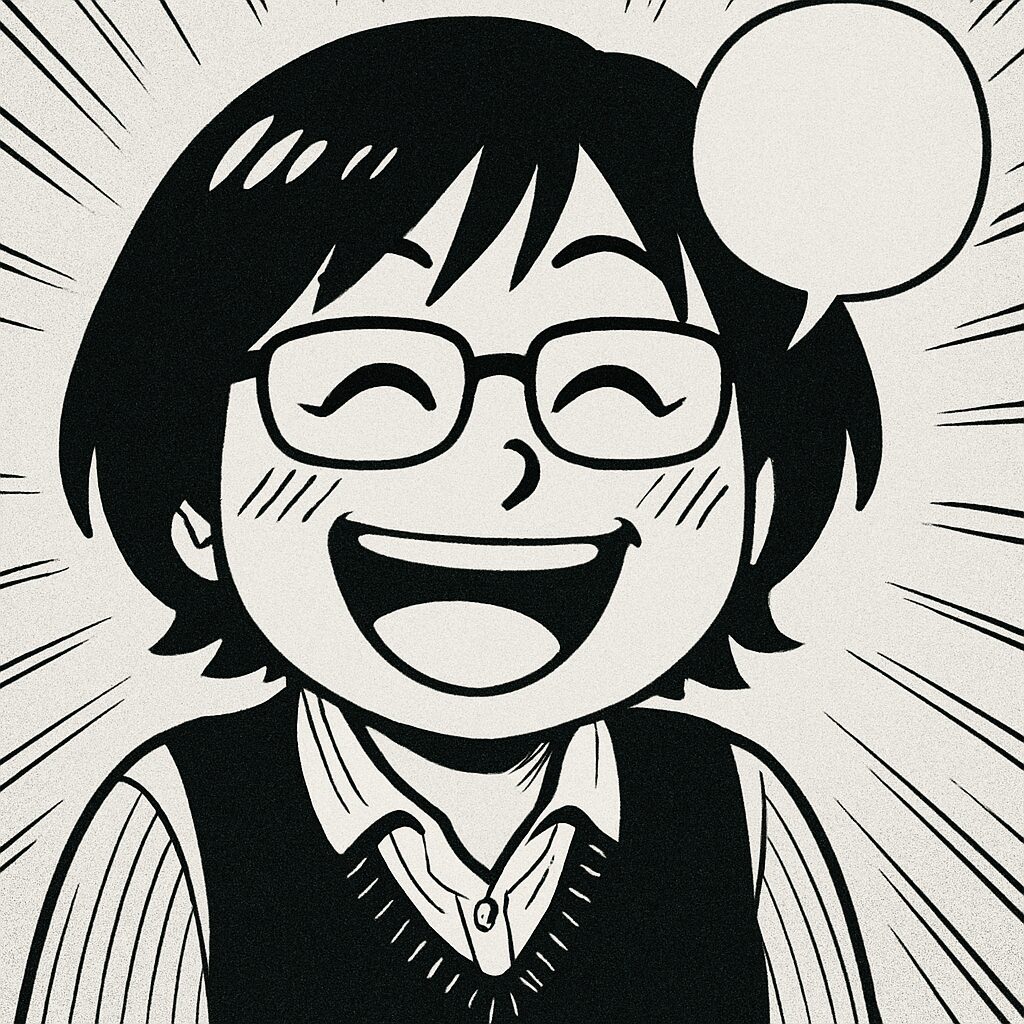
我が家でも、毎日の生活リズムはほとんど同じです。
「そろそろごはんかな?」「お散歩の時間!」と感じる時間があることで、安心するようです。
② 住環境をシンプルに
認知機能が低下すると、空間把握が難しくなります。
家具の位置を頻繁に変えず、段差や角をやわらかい素材で保護しましょう。
- 床に滑り止めマットを敷く
- 動線に物を置かない
- 夜は常夜灯でぼんやり明るく
飼い主さんが外出する際は、円形サークルなどを設置し家具への衝突や挟まりを避けるような工夫をすると安心です。
③ 脳を刺激する“日常の工夫”
認知機能を保つには、軽い刺激が効果的です。
- におい探しゲーム(おやつを隠して探す)
- 新しい散歩コースを少し歩く
- 名前を呼んでスキンシップをとる
- 日光浴をする
こうした“日常の変化”が脳の活性化につながります。
天気の良い日中にお庭などで日向ぼっこをするなど日光浴は認知機能低下による脳の刺激に非常に効果があると言われています。
④ 不安をやわらげる夜のケア
夜間の徘徊や夜泣きが出てきたときは、
環境と安心感の両面からサポートを。
- 常夜灯をつけて暗闇を減らす
- 飼い主さんの匂いのあるタオルをベッドに置く
- 穏やかなBGMや人の声を流す
我が家では、夜はYouTubeのBGMチャンネルを小さく流しています。
いろいろな音楽チャンネルがあるので、わんこのお気に入りを探すのも楽しいですよ。
静かな夜にやさしい音が流れるだけで、安心して眠ってくれます。
👉 関連記事: シニア犬の夜泣き対策5選|原因と不安をやわらげる優しい工夫
⑤ 食事とサプリで脳の健康をサポート
脳の健康を保つ栄養素として、
**DHA・EPA・ビタミンE・MCTオイル(中鎖脂肪酸)**などが知られています。
- サーモン・青魚・卵黄などを食事に取り入れる
- 無理のない範囲でサプリを活用(獣医師と相談)
我が家でも、シニア期に入ってからはえごま油を少量取り入れています。
体に負担をかけずに、脳や皮膚の健康をサポートできるのでおすすめです。
👉 関連記事: シニア犬におすすめのフード選び|年齢と体調に合わせたごはんの工夫
飼い主さんの心のケアも大切に
介護期が近づくと、
「昔のように元気だった頃を思い出して切なくなる」
そんな気持ちになることもあります。
でも、今のわんこに必要なのは「昔の姿」ではなく、
**“今の姿を丸ごと受け止めてくれる存在”**です。
今日もちゃんとごはんを食べた
自分で立ち上がった
名前を呼んだらこっちを見てくれた
そんな小さな喜びを積み重ねることが、
飼い主さんとわんこの心の支えになります。
私も、最初の子の介護期には思うようにいかないことばかりで、毎日泣いていました。
でも今振り返ると、あの時間こそが一番あの子と向き合った大切な時間だったのだと思います。その経験が、今では他の子たちへの優しさにつながっています。
まとめ|“できること”を一緒に見つけていこう
認知機能の変化は、避けることはできません。
けれど、気づいてあげること・受け入れること・寄り添うことで、
わんこは穏やかに日々を過ごすことができます。
「もうできなくなった」ではなく、
「まだできることがある」——そう思えるだけで、
介護の時間は愛おしい絆の時間に変わります。
焦らず、比べず、ゆっくり。
今日も一緒に過ごせるこの時間を、大切にしていきましょう
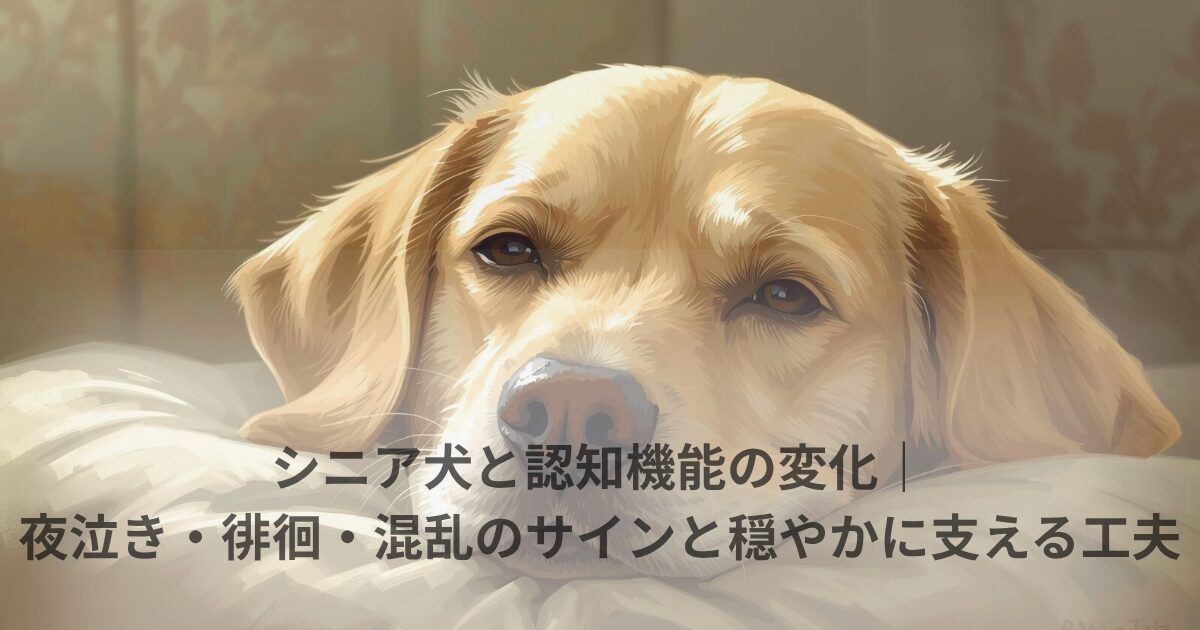


コメント